数ある環境問題の中でも、最も関心の高いとされる海面上昇。平均気温の上昇によって氷河が融け、また海水の膨張によって海面が上昇します。
高潮や洪水が頻発し、さらには水没・・・といった事態も避けられないでしょう。100年後の未来には、私たちの想像をはるかに超える事態が待ち受けているのかも知れません。
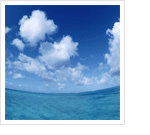 まず、海面上昇が起こる仕組みについて説明します。地球温暖化に伴う海面上昇は、おもに氷(陸上の氷河や氷床に貯蔵されていた氷など)の融解が原因とされています。
まず、海面上昇が起こる仕組みについて説明します。地球温暖化に伴う海面上昇は、おもに氷(陸上の氷河や氷床に貯蔵されていた氷など)の融解が原因とされています。
融け水や氷山などが海へと流れ込み、海水量が増えることで上昇する・・・ということです。また、水温上昇による海水の膨張も原因といえます。
ここで1つ気になるのが、近年ニュースなどでもよく報じられている北極海の氷です。北極海の氷が解けた際、海面は上昇するのか・・・簡単な実験で調べてみましょう。
まず氷の入ったコップに水を注ぎ、その氷が解けたときに水はあふれるのか観察してください。そう、これは“アルキメデスの原理”です。もちろん、コップから水があふれることはありません。要するに、北極海の氷とその融解は海面上昇と結び付かないのです。
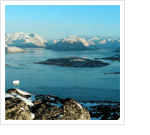 今、地球では一体何が起きているのでしょう? 南極の氷床(氷の本体)が融け、グリーンランドにある雪の堆積面積はここ数年で約20%も減りました。
今、地球では一体何が起きているのでしょう? 南極の氷床(氷の本体)が融け、グリーンランドにある雪の堆積面積はここ数年で約20%も減りました。
他にも棚氷の流失や永久凍土の融解、氷河の後退など各地で異常事態が相次いでいます。これらの影響を受けて、19~20世紀の100年間で平均海面水位が17cmも上昇しました。
また、2080年までに約40cmの海面上昇があると仮定した場合、被害を受ける人数は最大2億人とも予測されています。自分さえ助かれば、また自分の国さえ水没しなければ・・・という考えはもはや通用しません。
※注釈
南極大陸の氷は年々減少傾向にあるとされていますが、実は減少する氷よりも増加している氷の量のほうが多いという研究結果が、2015年にアメリカ航空宇宙局(NASA)のチームより発表されました。
研究結果によると、西南極の一部では氷の減少が進んでいる一方で、東部や内陸部の一部では増加傾向という結果が出ています。
増加の原因は、はるか昔からの降雪量が影響していると考えられています。
とはいえ、西南極では氷の減少スピードが速まっているものの、研究結果発表の時点で増加スピードは緩やかになっています。このことからも、今後は徐々に氷の減少量が増加量を上回っていくことが予想されるでしょう。
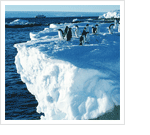 地球温暖化が進むと、南極の氷床は厚くなると言われています。これは水の循環が活発になることで、南極の降雪量が増えるからです。
地球温暖化が進むと、南極の氷床は厚くなると言われています。これは水の循環が活発になることで、南極の降雪量が増えるからです。
一方、2002年には南極の棚氷が3,250平方キロメートルという広範囲にわたって崩壊しました。これは過去12,000年間で最大規模とされています。
地球温暖化は南極に比較的暖かい夏をもたらし、こうした崩壊が進んでいると考えられています。また、地球温暖化によって暖められた海水が膨張し、海面上昇を引き起こす・・・といった見方もあるでしょう。どちらにしても、地球温暖化が大きく影響していることに変わりはありません。海面上昇を防ぐには、まず地球温暖化に歯止めをかけることが先決です。
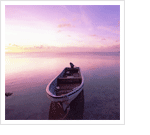 このままいけば、私たちの住む陸地は確実に減少します。日本の場合、1mの上昇によって海面下となる土地面積は2,339平方キロメートルにもなります。そこに住む人口は約410万人・・・と言えば、事の深刻さがわかるでしょう。
このままいけば、私たちの住む陸地は確実に減少します。日本の場合、1mの上昇によって海面下となる土地面積は2,339平方キロメートルにもなります。そこに住む人口は約410万人・・・と言えば、事の深刻さがわかるでしょう。
また、海面が1m上昇することで砂浜の約90%、40cmの上昇でも波打ち際から120cmほどの干潟が失われます。よって、砂浜や干潟を出産~保育の場とする海ガメをはじめ、
生態系全般への影響も避けられません。
しかし、これは日本のみならず世界中の沿岸地域に言えること。中でも、南太平洋の島々は深刻です。9つのサンゴ島からなるツバルは、世界で最初に沈む国とされています。危機感を抱いたツバル政府は、住民の大移住を検討するなど具体的な対策に乗り出しました。
他の沿岸地域でも洪水や台風の規模またそれに伴う被害増大や砂浜の消失、井戸(地下水)に海水が入り込む・・・などさまざまな影響が考えられます。また、デルタ地帯にある人口密集地域(バングラディシュなど)では難民の大量発生も考えられるでしょう。
 ページトップへ
ページトップへ